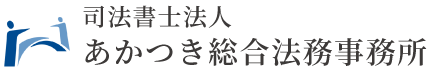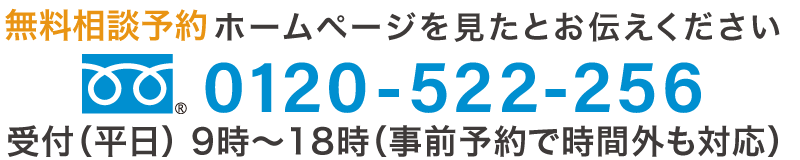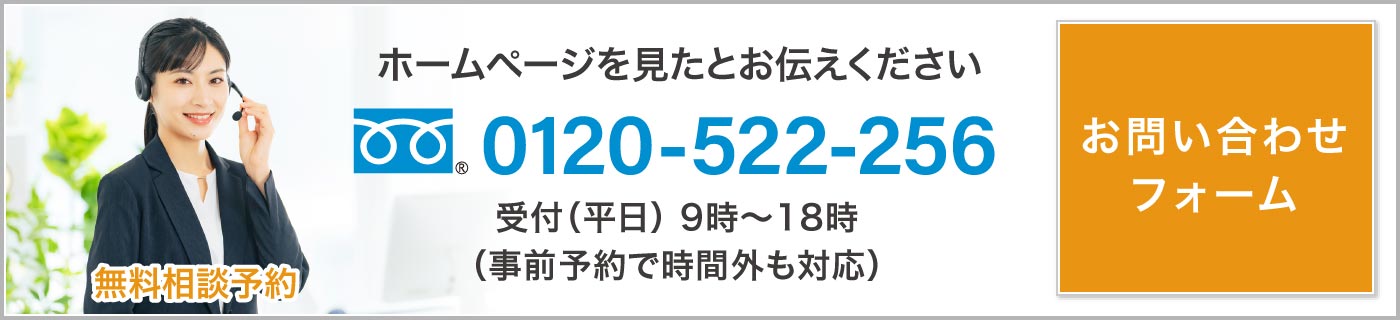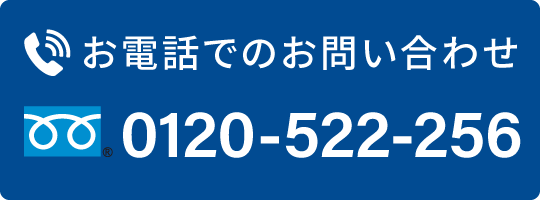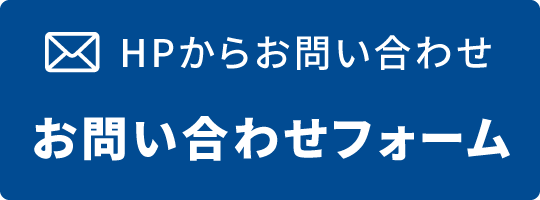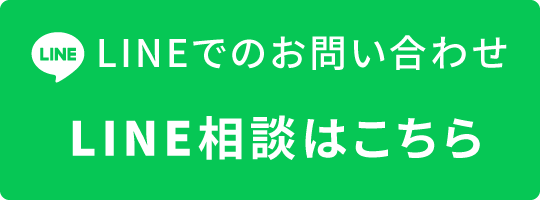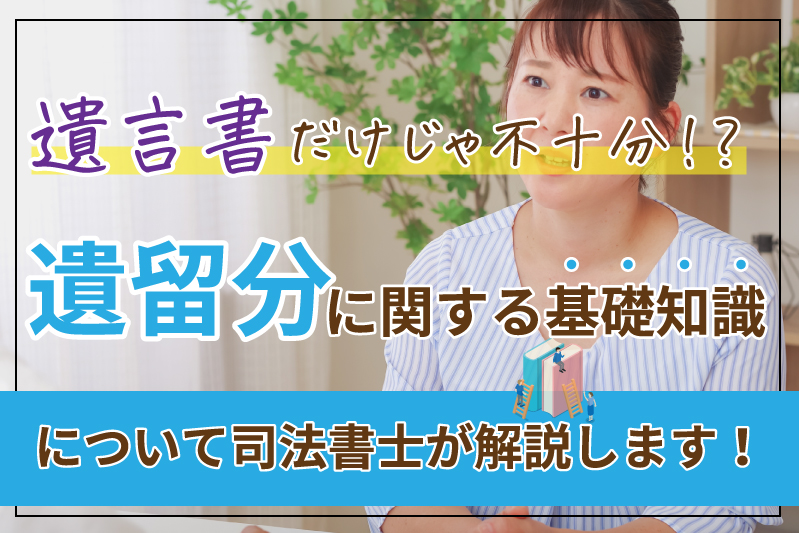
「遺言書を書いたのに別れた人との間の子供にも必ず財産を渡さなければならないの…?」
「甲斐性のない夫には一銭も財産を渡したくない…」
「遺留分も含めて相続・遺言書作成について専門家に相談したい…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
「うちは長男に家業を継いでもらうので、そのように遺言書を作ったから大丈夫…!」
「ずっと介護で世話になった長女に全財産をあげたい…だから遺言書にそうやって書いたから安心!」
そのようにお考えの方も多いと思います。
しかし遺言書を書いたとしても、特定の相続人には一定の割合の相続財産を金銭で請求できる権利があります。これを「遺留分」といいます。
遺言書を書く際には、この遺留分を必ず確保して作成しなければならないわけではありませんが、この遺留分を無視して遺言書を作成すると、後々親族間で相続の争い、いわゆる「争続(あらそうぞく)」に発展する可能性があります。
そこで以下では、計算方法をはじめ一定の相続人が有する遺留分について、解説してきます。
このページの目次
遺言があっても安心できない?遺留分の基本を解説
遺留分とは、一定の相続人について、亡くなった方の財産から法律上最低限取得できると保証されている割合のことをいいます。
亡くなった方が行った生前贈与や遺贈によって遺留分を受け取れなくなった場合には、遺留分を侵害されたとして、その侵害された金額に相当する金銭の支払を請求することができます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
誰がもらえる?遺留分がある相続人とその割合
遺留分は全ての相続人に認められるわけではなく、兄弟姉妹を除く相続人に限られます。
まず、総体的遺留分といって、相続人全体の遺留分を計算します。
総体的遺留分は、原則2分の1で、相続人が直系尊属(父母や祖父母)のみの場合には、3分の1になります(民法1042条1項)。
次に、総体的遺留分に相続人各々の法定相続分を乗じると、個別的遺留分、その相続人がもっている遺留分を計算することができます(民法1042条2項)。
以下では、典型的な例を3つご紹介します。
例1)亡くなった夫Aには、妻B・子供C・Dと、前妻との子供Eがいる場合
この場合、相続人は直系尊属のみではないので、総体的遺留分は2分の1となります。すると、個別的遺留分は、2分の1に法定相続分を乗じればいいので、妻Bは4分の1、子供C・D・Eは、それぞれ12分の1の遺留分を有することとなります。
Aの遺言書に「Aの遺産のうち、Bに2分の1、Cに4分の1、Dに4分の1を相続させる」と記載されていた場合、Eは、遺留分である12分の1について遺留分侵害額請求をすることができます。
例2)亡くなったAには、法律上の妻・子供がおらず、父B(母Cは既に死亡)がいる場合
この場合、相続人は直系尊属のみとなりますので、総体的遺留分は3分の1となります。相続人は、B一人なので個別的遺留分も3分の1となります。
Aの遺言書に「遺産の全てをDに遺贈する」と記載されていた場合には、Bは、遺産の3分の1について、遺留分侵害額請求をすることができます。
例3)亡くなったAには、妻・子供がおらず、兄Bがいる場合
兄弟姉妹には、遺留分は認められていませんから、Bには遺留分はありません。Aの遺言書に「遺産の全てをNPO法人Cに遺贈する」と記載されていた場合でも、遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分の計算方法と具体例をわかりやすく紹介
遺留分の計算方法について下記の例をもとに解説します。
亡くなったAの財産:相続財産5000万円、負債200万円
相続人:後妻B・前妻との子供CD
遺言書の内容:妻Bに全財産を相続させる
生前のAは、Dに対し、亡くなる1年前に1000万円を贈与した。
ステップ①:まずは相続財産の合計額に第三者に対しては原則相続開始前1年以内、相続人に対しては原則相続開始前10年以内の生前贈与を加え、債務を控除します
5000万円+1000万円-200万円=5800万円
ステップ②:①で計算した金額をもとに遺留分を計算します
Cの遺留分=5800万円×1/2×1/4=725万円
Dの遺留分=5800万円×1/2×1/4=725万円
ステップ③:生前贈与・特別受益差し引き、請求できる遺留分を計算します
Dの遺留分(負債・特別受益を考慮)=600万円-1000万円=▲400万円(※)
※Dは遺留分を請求することができません
よくある誤解と注意点|遺留分請求で損しないための3つのポイント
遺留分に関しては、以下のような注意点があります。
遺留分を侵害する場合でも遺言書は無効にはならない
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる権利ではありますが、だからといって遺留分を侵害する遺言書自体が無効になるわけではありません。
遺留分を侵害した内容であったとしても、遺言書自体は有効です。
遺留分侵害額請求には請求期限がある
遺留分はその権利の性質上、非常に短い請求期限が定められており、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、相続開始の時から10年以内に請求する必要があります(民法1048条)。
遺留分侵害額請求を行う場合には、この期間内を過ぎると請求することができなくなるため、注意が必要です。
金銭でしか請求できない
遺留分については、2019年7月以降は遺留分侵害額の請求しか行うことができなくなりました。
そのため、仮に遺留分を持つ相続人以外の者に不動産や有価証券などを相続・遺贈させる内容の遺言書があった場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害した相続人に対して金銭の請求を行う他ありません。
突然の通知書…⁉遺留分を請求されたらどうする?冷静に対応するには
遺言書の内容が遺留分を侵害する内容となっている場合、あるいは特定の相続人に対し偏った生前贈与や特別受益を持つ相続人がいる場合には、前妻の子供や義理の両親等から遺留分侵害額請求がくる場合があります。
ときには、弁護士などの専門家から通知書が届く可能性もありますので、その際には焦らず落ち着いてお近くの相続の専門家へご相談ください。
また、当法人の提携弁護士をご紹介することもできますので、遠慮なくお申し付けください。
“当法人の提携弁護士法人「弁護士法人アクロピース」のホームページをみる”
まずはご相談ください!
他の相続人から遺留分侵害額請求の通知書がきた、あるいは今後相続のことで揉めそう、という場合には不安になる方もいるかと思います。
当法人では、家庭裁判所への提出書類の作成も行っておりますので、裁判所提出書類のことなら司法書士法人あかつき総合法務事務所までお問い合わせください。
LINEで相談|登録いただいたお客様に「相続対策総合ガイド」をプレゼント!
これから起こる相続、あるいは今発生している相続について、様々なご心配をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そのようなお客様のお悩みを解決するべく、当法人では現在「LINE相談」を実施しております。
「LINE相談」をご利用いただく際には、当法人の公式LINEにご登録いただく必要があります。
今ならご登録いただいたお客様全員に相続に関する網羅的な知識を獲得できる「相続対策総合ガイド」をプレゼントしております。
是非この機会にお友達登録をお願いいたします!
提携弁護士をご紹介いたします!
相続の事案によっては既に相続人間で争っている、いわゆる「争族」になっているケースもございます。
当法人は司法書士法人であるため、上記のような事案は対応できない場合もあるかもしれません。
その際には、当法人より相続に注力する弁護士のご紹介も承ることができますので、まずは当法人までお問い合わせください。
“当法人の提携弁護士法人「弁護士法人アクロピース」のホームページをみる”
その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、“投稿記事【相続手続・遺産承継業務】”をご覧ください。
監修者情報

相続や離婚、家族信託に関する豊富な知識と経験を持ち、遺産相続のみならず、生前の相続対策など多くの相続相談に対応。
特に不動産を含む資産の相続に強みがあり、丁寧な対応とわかりやすい説明で定評があります。
当法人とも連携し、相続案件に関するサポートを行っています。
弁護士法人アクロピースのホームページ:https://acropiece-lawfirm.com/