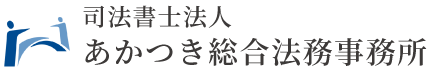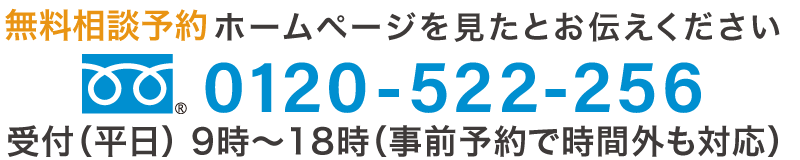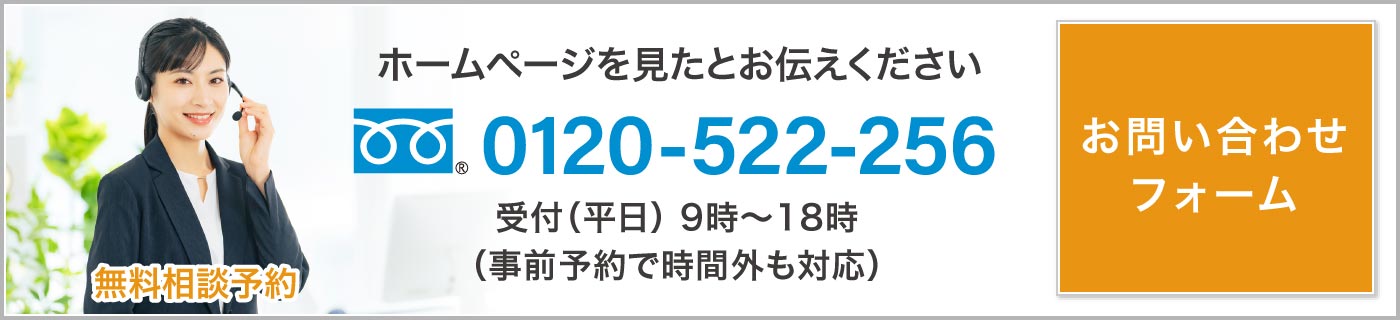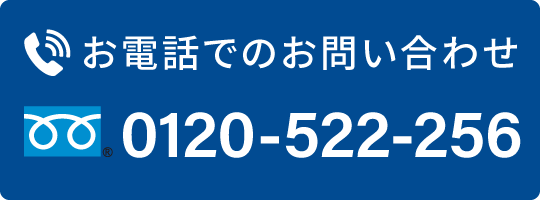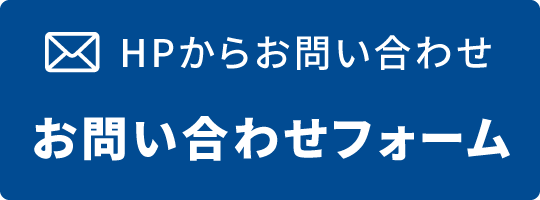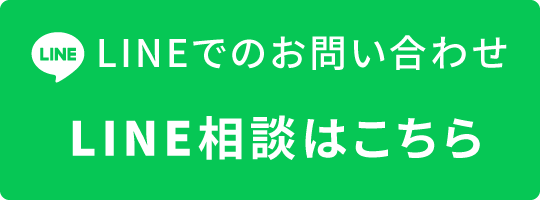「相続した不動産って、どうやって評価するの…?」
「不動産評価を間違えると税金で損しないか不安だ…」
「不動産の評価も含めて、相続の専門家に相談したい…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
令和5年分「相続税の申告実績の概要」によれば、不動産は相続財産の金額の構成比の中で、36.5%(土地:31.5% 建物:5.0%)を占めており、相続手続きにおいて、不動産の取り扱いはとても重要になります。
特に相続不動産は、評価方法が複雑なため、評価を誤ると高い税金を支払い、あるいは相続人間の揉め事の原因にもなるため、注意が必要です。
そこで相続税が発生する場合、あるいは相続人間できちんと遺産分割協議を行う場合には、相続税専門の税理士や不動産会社等に不動産の評価を依頼することが重要になります。
以下では、相続した不動産の評価方法と評価するうえでの注意点について、当法人の提携税理士である、木村聡子先生監修のもと、解説してきます。
このページの目次
【相続税・売却・登記】 相続した不動産における3つの評価方法とは?
相続した不動産の評価額は、相続税の算定根拠となる「相続税評価額」と登記名義の変更を行うときに使用する「固定資産税評価額」、不動産を売却するときに参考となる「不動産時価額(実勢価格)」の3つ分けられます。
それぞれがどの場面で使用するべきか、目的ごとに正しく理解しておくことが重要です。
以下、それぞれの評価額について解説します。
相続税評価額について
相続税評価額とは、相続税の申告・納税のために使用される評価額のことをいいます。
国税庁が定めた「財産評価基本通達」に従い、土地と建物それぞれに評価ルールが存在します。(国税庁のホームページはこちら)
土地の評価方法
相続税評価における土地の評価方法には以下の2種類があります。
① 路線価方式
路線価方式とは、国税庁が毎年発表している「路線価図」に基づいて、土地の面する道路ごとに定められた単価(1㎡あたり)をベースに評価する方法です。
住宅街や都市部など、多くの地域でこの方式が適用されます。
【例】
ある土地の路線価が200,000円/㎡、面積が100㎡なら、評価額は20,000,000円となります。
なお、土地の形状(いわゆる「不整形地」等)・間口・奥行・接道状況(いわゆる「セットバック」等)によっては、「補正率」が加味されることがあります。
② 倍率方式
倍率方式とは、地方など路線価が設定されていない地域では、固定資産税評価額に一定の「倍率」をかけて算出する方法です。
倍率は「倍率表」で公開されており、市区町村ごとに異なります。
【例】
固定資産税評価額:5,000,000円、倍率:1.1倍の場合
→ 相続税評価額 = 5,000,000 × 1.1 = 5,500,000円
建物の評価方法
建物については、「固定資産税評価額」をそのまま相続税評価額として使用します。
この評価額は、市区町村から送付される「固定資産税納税通知書」または「固定資産税課税明細書」で確認可能です。
固定資産税評価額について
固定資産税評価額とは、市区町村が課税目的で定める評価額であり、固定資産税や都市計画税の計算根拠になる評価額のことをいいます。
相続登記を行う際の登録免許税の計算にも使用されますが、相続税の計算とは異なるため注意が必要です。
※登録免許税の計算方法については、【相続登記をするときの登録免許税の計算方法について】の記事をご覧ください。
【補足】
- 建物の場合、評価額は新築時に決定され、評価替えの基準年度(3年ごと)に見直されます。
- 土地の場合、周辺環境の変化(駅の新設など)によって評価額が変動することがあります。
不動産時価額について
不動産時価額とは、実際にその不動産を市場で売却した場合の取引価格のことをいいます。
相続税評価額よりも高くなる傾向があり、不動産を売却する場合や、相続人間での分割を行う場合にはこの価格が基準になります。
【実務上の注意点】
- 相続開始時点での「近隣取引事例」や「不動産会社の査定書」が参考資料となる
- 時価を重視するなら、複数の業者に査定を依頼するのがおすすめ!
相続した不動産の評価が重要な理由とは?
相続した不動産の評価が重要なのは、① 相続税の計算に影響がある、② 相続人間で平等に遺産分割するときの資料となる、③ 売却や活用のための重要な資料となる、といった点が挙げられます。
以下、それぞれ詳細を解説していきます。
① 相続税の計算に影響がある
相続税は「相続税評価額」に基づいて税額が決まるため、正しい税申告をするためには、正確な不動産評価が必要になります。
正確な評価をすることができなければ、不要な納税をしてしまう、あるいは税務調査により追徴課税が課されるリスクがあります。
② 相続人間で平等に遺産分割するときの資料となる
現金や預貯金と違い、不動産は相続人間で分割が難しい資産です。
たとえば、長男が不動産を取得する代わりに、次男に相応の現金を渡す「代償分割」という方法で分割を行う場合、正しい評価ができていないと不公平感が生まれ、争いの種になります。
③ 不動産の売却や活用のための重要な資料となる
相続した不動産を今後どのような形で残していくのか、あるいはゆくゆくは売却していくのか、不動産は重要な資産というだけでなく、ご家族の今後の人生設計の重要なツールであると言っても過言ではありません。
そのためにも、「現状所有している不動産が一体いくらくらいの価値があるのか」を知っておくことはとても大切です。
※相続した不動産を売却するときの流れと注意点については、【相続した不動産の売却完全ガイド|流れ・税金・高く売るコツを司法書士が解説】をご覧ください。
相続した不動産の評価をするための流れと手順
相続した不動産の評価額を調べるためには、① 登記簿謄本や登記情報提供サービスを用いて不動産の種類・場所を確認し、② 固定資産評価証明書や公図等、必要書類を取得し、③ 路線価図・倍率表をチェックし、④ 必要があれば税理士等の専門家に不動産評価を依頼する、という流れになります。
以下、詳細を解説していきます。
① 不動産の種類・場所を確認する
まずはご自身の所有している不動産の種類や場所を確認します。
不動産の現在状況は管轄の法務局で取得できる登記簿謄本や一般財団法人民事法務協会が提供する登記情報提供サービスより確認することができます。
② 必要書類を取得する
不動産の状況が把握できたら、不動産の固定資産税の評価額が記載されている固定資産評価証明書等の必要書類を取得します。
場合によっては、ご自身では把握していない私道を所有していることもあるので、公図を取得しておくこともおすすめです。
③ 路線価図・倍率表をチェックする
一通りの必要書類を取得したら、ご自身所有の土地の路線価あるいは倍率表をチェックします。
お持ちの土地によっては「補正率」や「地積規模の大きな宅地の評価」など特例評価が適用されるケースもあります。
④ 専門家へ不動産評価を依頼する
相続税が発生する可能性がある場合は、必ず税理士や不動産鑑定士など専門家に相談しましょう。評価誤りは過少申告・税務調査リスクに直結します。
不動産の評価は誰に依頼すべき?司法書士・税理士・不動産会社の役割とは
「結局、相続した不動産がある場合、その評価は誰に相談したらいいの…?」
不動産に関する専門家は、司法書士をはじめ、税理士や不動産会社など、様々な相談先があるため、迷われる方もいらっしゃるでしょう。
以下では、相続不動産の評価に関する相談先について解説します。
① 司法書士へ相談する
司法書士は不動産の権利関係に関する手続き(登記名義の変更等)の専門家ですが、不動産の評価自体をできるわけではありません。
しかし、不動産の評価を行った後は必ず名義変更等の手続きを行うことになりますし、普段から税理士や不動産会社と連携して仕事をしている司法書士事務所も多いです。
そのため司法書士へ直接依頼すれば、相続した不動産の名義変更を行うだけでなく、その不動産の評価を提携の税理士や不動産会社へ依頼することが可能となり、ワンストップでお客様のお悩みを解決することができます。
② 税理士へ相談する
税理士は相続税申告の専門家のため、相続財産に不動産がある場合、相続税評価額をもとに不動産を評価します。
不動産の評価額によって相続税の額に大きな影響があるため、相続税申告が必要になる場合には、税理士へ依頼することを強くおすすめします。
③ 不動産会社へ相談する
相続人間で遺産分割を行う際、「実際に売却したらいくらになるか」が判断基準になる場合があります。
その際には、不動産会社へ査定をお願いして、時価額を調べることができます。
なお、「どの会社へ依頼すればいいか分からない」という方は、当事務所提携の不動産会社へ査定を依頼いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
④ その他の専門家へ相談する
既に相続人間で揉めている等の事情により、正確な不動産の鑑定を行う場合もあるでしょう。
また遺留分の算定のため、相続人の代理人として不動産の価格を調査する場合もあります。
上記のような場合には、不動産鑑定士や弁護士のような専門家に依頼する必要があります。
不動産評価をするうえで注意すべき3つのポイント
「不動産評価で注意した方がいいことはないの…?」
相続税やいわゆる「争族」対策のため、評価を誤ることはできないため、不動産評価をするうえで、不安なこともあることでしょう。
以下では、不動産評価をするうえで、注意すべき3つのポイントについて解説していきます。
① 不動産分野に強い専門家に依頼する
意外に思われるかもしれませんが、税理士や司法書士、不動産会社などの不動産の専門家全てが相続に強いわけではありません。
「相続専門」「不動産評価の実績多数」などの実績を確認したうえで、理想を言えば、専門家同士が協力し合ってお客様のお悩みを解決できるサービス提供を行っている専門家が望ましいです。
② 申告時期や期限に注意する
相続税の申告が必要になる場合、あるいは相続発生後不動産を売却する場合、一定期間内に申告手続きをする必要がある、あるいは一定期間内に売却手続きをすると節税の特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)を受けることができます。
③ 遺産分割や売却を見据えて総合的に判断する
相続した不動産は、ただ評価を行い金額を出せばよいというわけではありません。
今後「誰が」「いつまで」住むのか、売却するのであれば、「今」売却するのか、それとも「今後」売却するのか、そういったご親族の家族構成や年齢などの要素も考慮したうえで、どのように手続きをしていくかを決定していくべきです。
まとめ:相続不動産の評価は相続手続きの「最初の一歩」|専門家への相談をお早めに!
不動産の相続は、評価方法ひとつで大きな差が生まれる重要なプロセスです。
「まだ先のこと」と思わず、可能であればご生前から早めに信頼できる専門家に相談し、安心して相続手続きを進めることが大切です。
司法書士法人あかつき総合法務事務所では、相続不動産の評価をはじめ、相続登記や遺産分割協議のサポート、提携税理士との連携による相続税申告まで、ワンストップで対応いたします、「遺産承継一括お任せパック」がおすすめです!
遺産承継一括お任せパックは、198,000円からのご案内でき、不動産の名義変更はもちろん、預貯金の解約や株式有価証券の移管手続きなど、面倒な手続きをまるごと任せいただくことができます。
「父の相続手続きをゆっくりやる時間がない…」
「亡くなった兄の相続関係者が多すぎて、自分ではできない…」
「相続手続きを丸投げできる専門家に依頼したい…!」
というお客様は、当事務所の「遺産承継一括お任せパック」を是非ご利用ください!(遺産承継一括お任せパックの料金体系はこちら)
監修者情報

相続税・贈与税に関する豊富な知識と経験を持ち、相続税申告のみならず、生前対策など多くの税務相談に対応。
特に不動産を含む資産の相続に強みがあり、丁寧な対応とわかりやすい説明で定評があります。
当法人とも連携し、相続税申告・不動産評価に関するサポートを行っています。
YouTubeチャンネル 【小さな相続専門TV】税理士きむらあきらこ にて毎週月曜日20時に配信中。